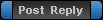| Author |
Message |
hjb4n0mbvft
Joined: 10 Sep 2013
Posts: 4724
Read: 0 topics
Warns: 0/10
Location: England
|
|
 iphone5ケース と& iphone5ケース と& |
|
とりちゅう
上蒜山登山口(8:14)五合目(9:24)八合目(10:07)上蒜山山頂(10:53)、しばらく三角点散策山頂出発(11:28)上蒜山登山口(12:46)、所要時間、4時間32分
飴が雪上を滑り落ちていきます。水気を含んで重たいはずなのに、表面は滑りやすくなっていたのです。私はその前もって決められていたかのような落下を凝視していました。そして見えなくなってしまいました。「まさか落ちるなんて……」。進む先を見ると登山道に亀裂が入り、少し離れたところでは雪崩が起こっています。まさかね……、という言葉が頭の中で反響しています目指す上蒜山は1202メートル。蒜山三座の中では一番高いです。上蒜山駐車場に車を停めます。スキー場の横を通っていくと登山口までのアクセスが短縮できますが、ここを歩いてよかったのかは分かりません。もし駄目だったのなら申し訳ないです今回同行してくれるのは、妖怪G君。頼れる山登りの相棒です。ワカンを履いています。一方で私はアイゼン。「ワカンがいい。一番いいのはスノーシュー」というG君と「いや、しばらく目立った降雪はないらしいし、稜線でたら冷えてるしでアイゼンで大丈夫だらあ」という私の意見が対立。果たしてどちらが効率的でしょうか一ニ合目くらいまでは杉が目立ちます。樹木地帯の中はまずまずはまり込みます。「やっぱりワカン履いてきた方がよかったか」と早くも泣きモード。明らかに歩行スピードが違います。ここは先にいってもらう作戦にでました。私はトレースを辿るだけのトレース泥棒。この辺はルートが不明瞭なので、正規ルートを進まず、とりあえず上を目指しました。なんとか赤テープがある登山道にでることができました三合目付近までくると麓の蒜山高原を望むことができます。この辺で小休止。私のウエストバックに入っていた飴をG君に投げます。が、彼まで届かず手前に落ちてしまいました。そしてしばらくは雪の上に停まっていましたが、10秒ほど経過したとき、思い立ったように滑り落ちていったのです。滑落していく飴。レモン味。何かを暗示しているような気がしました再び歩き始めるとこの日はじめて晴れ間が差してきました。樹木帯をでた開放感と、温かみを与えてくれる太陽のおかげで気分も陽気になり、お互いの発言も多くなります。あとは尾根伝いにいけば山頂まで迷うことはないはずです雪崩の巣の五合目を登りきると稜線上にでます。そこからは一転、雪庇の連なりが続きます。そしてそれは登るごとに大きさを増していきます。南側にこんもりとしたかわいらしさを携えつつも、実は踏み抜いたらただではすみません。甘い罠ですここからはどんどん悪天候、悪条件になっていきます。地面には気づいたらクレバスが口を広げています。視界は不明瞭になり、積雪の切れ間があいまいになっていきます本来なら上蒜山随一の展望がいい八合目の槍ヶ峰も真っ白。「八合目」と書かれた木の柱がほとんど埋まっており、掘り起こして確認します。積雪は二メートルはあるでしょうか降雪も勢いを増してきました。ハードシェルのファスナーをしっかり口元まで締めます。さすがに稜線上、普段から寒風が吹いているんでしょう、アイゼンでもそれほど踏み込みませんでした。ただし、ここまではワカンの勝利です。やっぱりはまり具合が違います八合目付近からはブナの樹氷が目立ち始めてきましたブナを横目に雪庇を踏み抜かないように歩いていると、油断したのか、なんとG君が尾根から滑落しました。まさか……。序盤で滑り落ちていった飴が脳裏を過ぎります。G君も飴と同じようにあたかも決められていた出来事のように滑っていったのですなどと大げさに書きましたが、まったく対した滑落具合ではありませんでした。半ば落ちるつもりで滑ったようです山頂には10時55分に到着。2時間41分かかりました。無積期の山頂は樹木に囲まれており、ほとんど展望がなく、蒜山三座の山頂でももっとも閉塞感に包まれ、人気もない場所です。ただし、積雪期の上蒜山の頂は、それまで通るときに見てきたものとは比べ物もならないほど発達したブナの樹氷に囲まれていたのです今回はネックシャツの上にハードシェルを重ね、二枚で登りました。アイゼンでも登れないことはないですが、やはりスノーシューかワカンの方が無難でしょうねえ下る最中のG君はピッケルと小さなソリを持っていました。尻セードで滑りながら下るのが目的のようです。雪庇が真横にある地帯も構わず滑るものだから始末に終えません○関連記事
とりちゅう:急ぎ足で蒜山三座縦走往復してみた
「蒜山ごるじい」さん:スノーシューで上蒜山登山雪庇はそこそこ大きくなっています
パソコンの中でうっとりしていた光景が今まさに私の前に広がっています,[url=http://www.iphonecaseshopjp.com/]iphone5ケース[/url]。上半身がぞくぞく。震えを感じます。ラクダの背、そしてその先の剣ヶ峰が遠くに見えます。どこまでいけるのか,[url=http://www.iphonecaseshopjp.com/%E3%83%AB%E3%82%A4%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%88%E3%83%B3iphone-5-%E6%90%BA%E5%B8%AF%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9-c-4.html]ルイヴィトンiPhone5ケース[/url]。トレースに頼ることになります。南側に雪庇が張り出しています。そこでトレースが消えていたので唖然としました。幸いにして北側斜面の角度がそれほどではなかったので、ピッケルを突き刺して回り込むようにして歩いていきます。雪質はまずまずしまっています。小動物の足跡があったのが驚きです。キツネかタヌキか尾根を歩く恐さよりも踏み抜く恐さの方が強かったです。樹木に雪がかぶさって積もり、中途半端に空間ができているのです。踏みぬいたらおそらく這い上がることはできません。小さなクレバスもできており、大股で越えるようなこともしましたそして稜線の核心部、ラクダの背の前まできました。ここでトレースが復活しています。しっかり踏み跡を辿って、まずは「背」の部分を登ります。右は雪庇、左は急斜面。どちらに転んでもただではすみません。ラクダの頭と背の間が一番の難所でした。積雪期でもこれほどの細尾根です。南側では氷壁から雪の塊がはがれ落ちそうになっておりました。ラクダの頭を越えても、しばらく神経をつかう歩きが続きます。中腰で一歩一歩踏みしめます剣ヶ峰に到着。広い台地になっておりました。碑は雪で埋もれて確認できませんでした。トレースがなかったらここまでくることができませんでした。先行者に感謝します南側には槍ヶ峰の尾根が伸びています。誰も歩いていません。ユートピア方面に歩いていく予定もありましたが、トレースがありません。雪庇も発達しており、今の自分の知識、技術では滑落の恐れもありましたので本日はここまでとしました再び弥山まで帰るのが普通です。が、ラクダの背と剣ヶ峰の間の北側に伸びている尾根にトレースがあるのに気づきました。「歩けるところまで下るか」とトレースを辿って下っていきます。まずまずの急斜面なので、しっかりとピッケルで突き刺し、アイゼンで踏みしめるのも肝要です次第に斜度が増してきて、最も急なところでは40度はあったでしょうか。こうなると後ろ向きで降りなくては危ないです。前向きだと滑ってそのまま落ちてしまう可能性があります,[url=http://www.iphonecaseshopjp.com/]iPhone5 ケース おしゃれ[/url]。アイゼンの前歯二本をグサグサしっかりと突き刺します。グローブをはめた左手も雪壁にめりこませます。途中の沢をトラバース(斜面を横断)するところでトレースが消えていましたが、そこからは斜度も幾分緩やかになってきました。遠くには元谷が見えます。眼前には大屏風岩の西壁がものすごい圧力をもって目に飛び込んできました。上空では飛行機が煙を残して飛び交っています。剣ヶ峰沢と合流するところからはお尻をついて滑っていきます。「雪崩れ起きるなよ」と願いつつ、ザザーと面白いくらいに滑らかに滑りました矢印が降りてきたルートです。こんなルートがあったのか。積雪期限定でしょうねえ。帰ってから調べてみましたが、下ってきた沢の名前が分かりません。ラクダの背の横の沢なので、ラクダ沢といってもいいんでしょうか。
The post has been approved 0 times
|
|
| Mon 18:51, 25 Nov 2013 |
 |
 |
|
|
 |
|
|
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
|
|
|